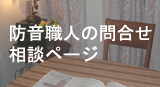木造住宅の防音(構造・仕様と空間計画の考え方)
住まいの防音は、下地の構造と空間構成が大きな鍵を握っています。木材と防音材の力を高める設計が必要です。
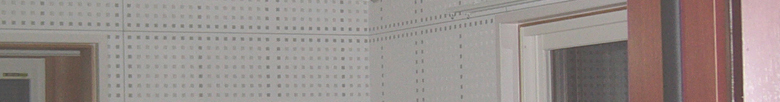
防音と構造的な補強

木造住宅は、構造上、防音性能が低いと施工業者や建築士がよく言いますが、その認識は間違っています。
遮音性に全く配慮していない構造を設計して、施工するからです。
特に問題なのは、下地の耐久性・制振性および壁内・天井裏・床下に使用する吸音材(断熱材)です。
例えば、吸音材(断熱材)に隙間があったり、沈下の割合が多い素材や工法を選択したり、発泡材を使用すると遮音性能が低下します。
素材の性能や下地の補強などに十分に配慮した構造を設計し、適正な工法で施工すれば、木造家屋でも遮音性を十分に高めることは 可能です。
木材は、吸音性や衝撃をある程度吸収する性質があり、軽量鉄骨のように過度な反響や共振をしないので下地としても 非常に適しています。また、構造的な補強により、制振性能を高め、防音性能を向上させることができます。
防音と建物の空間構成
木造住宅では、壁などの厚さを必要以上に大きくしたり、重い遮音材を多量に使用することは、下地が歪むなどリスクがあり、費用対効果の
低い防音、使い勝手の悪い居住空間となります。
*参照ページ:防音材の種類と特性
木造家屋では、収納棚やギャラリー、回廊などの緩衝空間をうまく配置することによって、遮音性を高めることが出来ます。
特に、新築住宅や大規模リフォームでは、居室・収納スペース、人の動線、冷暖房・通気・窓などの配置を十分に検討することが重要です。
防音材と防湿・結露対策
木造住宅では、表層材の隙間を許容しながらも、快適で費用対効果の高い防音構造が望まれます。
このとき、問題になるのが隙間からの臭い・湿気や結露です。
例えば、床や壁の板張り仕上げは、隙間が出来ます。遮音性には一見不利なように感じますが、板材の持つ適度な吸音・反響を活かし、 下地に気密処理した遮音・制振材を施工しておけば、湿気を防ぎながら音響・防音の相乗効果が期待できます。
このため、防湿・気密と遮音性を同時に満足するリスクの少ない防音材、適切な工法が必要です。
また、床暖房を導入する場合は、熱によって臭いが揮発したり、劣化するような素材は避けなければなりません。適正な防音材を
選択して、遮音性・快適性・耐久性等に十分配慮すべきです。